<Black Card>
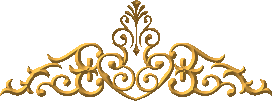
女王様は鏡の前で、もういくつめかになるバッグを選んでいる。
「よろしければどうぞ。」
「ありがとう。」
店員から勧められた椅子を、柔らかに断ることにもだいぶ慣れた。
泉田は、ソファーの背に軽く手をかけ、さりげなく目立たなく立つ。
そして時々振り向く涼子の視線をしっかりと受け止める。
お手本は、あの新宿御苑前のお店の前で会った、JACESの秘書室次長さん。
初めは右往左往、何をすべきか皆目見当がつかず、きょろきょろと
挙動不審だった泉田も、回を重ねるたびごとにすっかりお買い物のお供が板についた。
どうやら決まったようで、涼子が店員に気に入った商品を渡す。
この店では涼子は精算をしたことがない。
あとから請求がまとめてくるのか、いつくるのか、どうやってくるのか、泉田には見当もつかない。
――本当はここでこっちがカードを出せば、完璧なんだろうけど。
泉田は苦笑いを浮かべる。
しかしあのバッグ一個で月給は飛ぶ。とても払えるものではない。
「大丈夫、ねだる時にはちゃんと買えそうなものをねだるから。
給与査定は誰がやってると思ってるの?泉田クンの懐具合はお見通しよ。」
ぎくっ。
いつの間にか涼子が泉田の前に立っている。
また心を読まれたらしい。
「わかりやすいわね、キミの表情は。」
「…申し訳ありません。」
降参。
頭を下げる泉田の腕を、涼子は明るく笑いながら取った。
「ふふ、謝るところじゃないでしょ?お待たせ、行こ。」
どうやらここに至るまでに生み出した大荷物も、届けてもらうことにしたらしい。
2人で冬の日差しが眩しい通りに出る。
いつになく楽しそうに腕につかまっている涼子の横顔を見ながら、
荷物を届けることにしたのは、こうして腕を組んで歩けるからかもしれない…
そんな小さなうぬぼれに、泉田はまた苦笑いを浮かべたのだった。

しかし。
「どちらへ?」
「ん、ちょっと行きたい店があるの。あそこ、お昼食べましょう。」
きれいな指が指し示す先には、一目で高級とわかるフレンチ・レストラン。
「最近出来たらしいわよ。まぁ雑誌で取り上げられているうちが花よね、ランチ2万円からじゃ。」
「に、2万円!?」
泉田の声が上ずる。
もう一本指が少なければ、日本料理なら何度か見たことがある。しかし…。
「楽しみよね〜。」
「…はい。」
まさか自分の分くらいは出せとは言われないだろうが、自然に体が強張る。
動揺していた泉田は、涼子の瞳が無邪気にわらっているだけではないことに気づけなかった。

ウェイターが一分の隙もない完璧な動作で注文を取りに来る。
「お料理の味付けにお好みはございますか?」
「お任せするわ。食後にはコーヒーを。」
「かしこまりました。」
値段対比十分なのか不十分なのかもよくわからない内装と応対に、
食べる前からすでに精神的にも、物理的にも満腹で、疲労感さえ覚えていた泉田は、
涼子がバックから、手のひらに隠れるほど小さなコンパクトを出すのをぼんやりと見ていた。
「・・・?」
前髪を直しているのか?と始めは思った。
それにしても、涼子のそんな仕草は見たことがない。
・・・違う。
涼子は斜め後ろの席を写しているのだ。
そこには、30代くらいの2人の男性が座っている。
若さを差し引いても、高級レストランにふさわしい身なりと格だが、どこか目つきは鋭い。
上級官僚か、企業経営者か、それとも犯罪を生業としている男たちか。
泉田は涼子に視線を戻した。涼子はひたすらに鏡を見つめている。
その指がたわむれる髪の先に隠れた形のいい耳に、ワイヤレスの小さな小さな受信機が収まっている。
「・・・!?」
瞬時に感覚が鋭敏になる。
これは捜査なのだ。それもドラよけお涼お得意の盗聴。
こんな白昼堂々と。
彼らをいったいなぜ追っているのか、何を聞いているのか。
考えを巡らせた泉田は、ふと本能的に視線を感じた。
すぐには反応せず、グラスを眺めるつもりで視線を感じる方向へ意識を集中させる。
グラスの向こうに、一人のウェイターが涼子の仕草を後ろからじっと見ている様子が伺える。
立ち位置から考えると、涼子が見ている男たちのテーブルの担当のようだ。
監視役なのかもしれない。
だとすれば、悟られるのはまずい。
「け…。」
泉田はかけようとした声を飲み込む。
あの2人が何らかの犯罪に関わっているとしたら、ここで警察官であることを明かすのは得策ではない。
涼子は気付かずにまた鏡を見ている。
注がれる視線は、強くなる。危険だ。

「・・・涼子、やめなさい。」
泉田の静かな声に、涼子はぴくりと反応し、顔を上げた。
「やめなさい。こっちを見て。」
そこには穏やかに微笑んだ忠臣がいる。
だが、その瞳の奥にはかすかに緊張の色が揺れており、涼子ははっと鏡を閉じた。
しかし時すでに遅く、こちらを見ていたウェイターが2人の男に歩み寄る。
その気配を察した涼子は、小さく舌打ちをして立ち上がった。
後ろの男たちも立ち上がってこちらを向く。
どうやら対峙する気のようだ。
ウェイターがポケットからナイフを取り出し、こちらへ突進してくる。
「客を避難させて!」
そう叫ぶと、泉田はテーブルを飛び越えて、ナイフを持った男の腕を蹴り上げた。
ナイフが宙を舞うその向こうに、2人の男が銃を構えるのが見える。
「泉田クン、伏せて!」
その声に素直に伏せると、頭の上を椅子が飛ぶ。
2人の男はまともにそれを食らってよろめく。
そこに涼子が、泉田が駆け寄る。
あとはお決まりの大乱闘だ。

「…グルではないのね。」
「存じません!」
泣き声に、涼子は支配人の胸倉を掴んでいた手を離すと、肩をすくめた。
店は、すでにほんのひと時前までの様相を呈しておらず、その辺りに割れた食器や倒れたテーブルが散乱している。
泉田は、駆けつけてきた所轄警察署の刑事に、ウェイターと2人の男を引き渡した。
さしあたって傷害、銃刀法違反で十分だろうが、涼子曰く男2人には星の数ほどの前科や未摘発犯罪があり、
所轄警察署のおじさま方は、泣いて喜びそうだということだ。
「しょうがないわね…今回はJACESにつけるわけにはいかないし、
所轄に任せるとこの店がつぶれちゃうまで払わないかもしれないし…これで精算して。」
涼子はバックの中からカードを取り出し、まだ呆然自失の支配人に渡した。
「まずカードチェックだけかけて。被害を見積ったら、そこに請求しなさい。水増しなんかしたらただじゃおかないわよ。」
「あ!は、はい。」
一瞬目の前を流れていったカードは、表面が黒く光っている。
――ブラック・カード!
もはや都市伝説のような存在のカード。涼子ならもちろん持っているだろうと思っていたが、
泉田も見たのは初めてだ。
管理人があわててレジでカードチェックをかける。
その間、涼子はカード会社に携帯で連絡を入れていた。
おそらく、請求が来たら自分宛に電話承認を入れるように指示しているのだろう。
支配人が、電話の終わった涼子にうやうやしくカードを返す。
「確かに確認させて頂きました。ありがとうございました。今後ともごひいきに。」
「ナイフ持ったウェイターを雇わないならね。行きましょ、泉田クン。」
涼子はひらひらと手を振ると、店のドアを出る。
所轄警察の同僚たちに頭を下げながら、泉田もそのあとに続いた。

街ははや夕暮れ。
涼子は口数少なく、泉田も腕を貸したままお堀端までゆっくりと歩く。
そして水面の見える小さな東屋に腰をおろした頃には、もうすっかり風が冷たい時刻だった。
その風からかばうように、泉田は涼子の風上に立った。
「泉田クン。」
ちょいちょいと指で招かれて泉田がかがむと、涼子のしなやかな指がくいっとネクタイを直した。
「あ、ありがとうございます。」
「いいタイね、正統派British。よく似合ってるわ。」
「警視のご指導のおかげで目が肥えてしまいましたからね。とてもスーツまでは手がまわりませんが。」
週末、涼子に「買い物に付き合って」と言われたら、回る店を考えるととても安物の服は着られない。
一着一万円のスーツを織り交ぜながらだが、少しずつ『こういう時に着る服』が増えていく。
資金負担で、懐は寒風吹きすさぶ状態になるが、いいものはやはり身につけていてもいいと実感できる。
泉田も徐々にそんな買い物を楽しめるようにもなってきた。
「来週は、泉田クンの買い物に一緒に行ってあげる。」
「遠慮しておきます。財布の中身どころか貯金まで飛んでしまいそうだ。」
そう言えば。
泉田はふと涼子のカードのことを思い出した。
「あのブラック・カード、戦車も買えるって本当ですか?」
涼子はやれやれとため息をつきながら、肩をすくめた。
「限度額がないって言うのは本当よ。だけど戦車を、決済方法に関わらず
個人に売ってくれる業者があるなら、その業者の方にお目にかかりたいもんだわ。」
「…ごもっともです。」
泉田は自分の小市民ぶりを恥じた。しかし涼子は気にもとめずに話を続ける。
「戦車は買うよりも持ち込む方が大変なのよ。」
「はあ?」
「あたしだって買えるものなら買いたいわ、あと一台、二台。」
「え、ええ…っと。」
突っ込みどころ満載だ。
薬師寺涼子は戦車を欲しがっている、そしてそれは既に持っているものへの追加?
目を丸くする泉田を、涼子は首をかしげて見上げた。
「泉田クンがブラック・カードで欲しいものは何?」
「…何でしょう?」
それこそ新しいスーツ、いやいや、それなら手持ちのクレジットカードで十分だ。
車?いや、置場がない。じゃあ家ごと買うか?いや、それもまだ早い。じゃあ・・・・。
しばしくるくると頭をまわした後、泉田は深いため息とともに告げた。
「…私には、そのカードは必要ないように思います。」
なんて貧乏性なんだろう、使い道がない。所詮善良な一般市民であることを痛感させられる。
しかし、意外にも涼子は軽く頷いた。
「そうよね、あたしも今これで何か欲しいってわけじゃないもの。」
「そう・・・なんですか?」
「カード会社がこれしかくれないから持っているけど、ほとんど使わないわ。
カード自体を見慣れていないような店で使うのも何かと面倒だから、そんなに便利でもないの。
ステータスだと言う人も多いけど、こんなカードでしか証明できないステータスに魅力なんて感じないし。」
「なるほど。」
確かに、涼子がそのカードを出すのを今日まで見たことがなかった。
そんなものか、と泉田も納得する。
「これでなんでも望みが叶うってわけじゃないものね。たとえば部下が突然有能になるとか。」
涼子は泉田を見てクスリと笑った。
その笑顔に、泉田はこれだけは言っておかねばと口を開く。

「警視、僭越ですがお願いです。」
「内容によっては聞いてもいいわ。何?」
「極秘捜査をされる場合には、出来る限り事前にご相談願えませんか。
今日のように突然の出来事にきちんと対処できるほど、私は部下としてまだ完璧ではありません。」
「却下。」
「警視!」
「だぁって!泉田クン、極秘捜査って言って演技が出来るタイプじゃないんだもん。
嘘つくのも苦手だし、すぐ顔に出るし。」
「うっ…。」
それは確かにそうだ。泉田は一瞬ひるんだが、反論を試みた。
「しかし心構えくらいは出来ます。あまり台詞の多い役柄は無理でも、気付かせないくらいは…。」
「出来る?」
「…たぶん。」
声は小さいが、まだ抵抗を試みる泉田に、涼子は仕方ないといった風に頷いた。
「わかったわ、出来るだけ言うようにする。今日見つかったのはあたしのヘマだもん。
あたしも偉そうには言えないわよね。」
「すみません…私も、もう少し早く気がつけば。」
涼子がふと思い出したように泉田のネクタイをひっぱった。
「な、なんですか。」
「そう言えば今日昼、呼び捨てにされたような気がしたわ。」
「え?」
「上司を呼び捨てにするなんていい度胸よね。」
「あれは身分を気づかせない為に!…」
涼子は獲物を捕まえたライオンもかくや、といった風情。
夕闇の中、切れ長の瞳がきらりと光る。
「もう一度呼んでごらん。」
「え?」
「そうしたら許してあげる。もう一度。」
「…承服しかねます。」
あまりにも必死で、どんな声で呼んだのかも思い出せない。冷静になれば恥ずかしすぎる。
泉田はぎゅっと口をつぐんだ。
「呼ばなきゃ、このカードで薬師寺家の敷地内に泉田クン名義の家を建てて、そこから通勤させるわよ。」
…どんな脅しだ。
しかし妙に真実味も混ざる涼子の低い声での脅迫に、泉田もしぶしぶ小さな声でつぶやいた。
「涼子・・・。」
「聞こえないわ。」
涼子は泉田のネクタイを掴んだ手を離し、じっと顔を覗き込んだ。
その目の力に圧倒されて、泉田は半ば自棄になり覚悟を決めた。
「…涼子。」
呼びかけた途端に、頬まで熱くなるのがわかる。
しかし、目をそらすもんかと意地になって上司を見据えた次の瞬間、
泉田の視界に、呼びかけられた本人の幸せいっぱいの微笑みが広がった。
「はぁい。」
・・・それは反則だろう。
泉田は跳ね上がる鼓動を止めるすべもなく、
あでやかな花のような美しい笑みに完全に魅入られてしまった。
夜の帳が、二人を、そして街を包み込むようにゆっくりと下り始めた。
(END)

*お昼抜きでおなかすきませんか、お二人さん…と無粋なことを言ってみる管理人でした。
きっとこのあと二人でまたどこかに行くんだな、楽しんでねと思ってスルーしてください。
御来訪の皆様、いつもありがとうございます。新刊と短編を楽しみにしつつ、がんばりましょう。