<雪の夜に>
「寒っ。」
建物を出た途端、底冷えした空気が全身に突き刺さる。
都会の灯りに押され黒ではありえなくなった夜空も、心なしか今夜はくすんだ灰色がかっている。
これぞ冬。
天気予報はどうだったかな。
そうつぶやきながら、泉田はコートの襟を合わせた。
「行くわよ、侍従長。」
「はいはい。」
凍える風の中でも、涼子は颯爽と背筋を伸ばし歩く。
裁判事項の整理で少し遅くなった週末。
さて、今日は何にありつけるのだろう。
「泉田警部補って、ほんと薬師寺警視のSPみたいですね。最近は出勤から帰宅までご一緒だし。」
昼休み、貝塚がそう言った。
「そんなに俺を警備部の配属にしたいのか?」
泉田は冗談めかして、わざと冷たく答えた。
「え〜違いますぅ。行かないでくださいぃ。」
貝塚があわてて泉田の袖を掴む。泉田は笑顔を見せて、彼女の頭をぽんぽんと叩いてやった。
「SP・・・か。」
そんなことを思い出して歩きながら小さくつぶやくと、
泉田のすぐ隣を歩いていた女王さまはぴくりと眉を上げた。
「何?まだなりたいの?」
「そりゃ警察官の憧れでしょう?」
「あら、あたしはなりたくないわ。」
「・・・それは・・・そうでしょうね。」
ドラよけお涼が要人警護。
本人の意向もさることながら、組織として決してやらない人事だろう。
警備部長の首を1ダース、さらに警視総監の首を半ダースくらい用意できれば別だろうが。
「で、今日はどこへ行くんですか?」
話題を変えた泉田に、涼子は口の端に指をあてて考える仕草を見せた。
「う〜ん、ちょっと遅くなったから、しっかりご飯っていう気分じゃないわよね?
かといって、軽くチャイニーズ?ううん・・・いやいや、それなら・・・。」
街灯に輝く横顔が見せる様々な表情は、見ていて飽きない。
そしてそのうちポン、と手を叩くと、くいっと泉田の腕を引いた。
「決めた、今日は寒いからとにかくおいしいお酒を飲もう。いいところがあるんだ。」
その口調からすると、泉田は初めて行くところらしい。
一瞬、若林(ジャッキー!)のいる白水仙のような場所が頭をよぎる。
「・・・あの、警視。」
「心配しなくていいわよ。泉田クンが考えているようなところじゃないわ。」
「あ、はい。」
考えを読まれているらしい。
あからさまにほっとした泉田に、涼子は拗ねたまなざしを向けた。
「そんな顔するなら、ジャッキーも呼ぶわよ。彼の友人付きでね。」
「・・・私が悪かったです。」
「よろしい。」
しばらく歩いて、涼子は地下に続く、屋根のない煉瓦作りの階段を指し示す。
「ここよ。」

『A Drink before the War』
階段を下まで降りきったところで、木の看板が店の名前を告げる。
「デニス=レヘインの探偵推理小説ですね。邦題が確か・・・。」
「『スコッチに涙を託して』かな。さ、はいろ。」
促す涼子に、泉田は重厚な扉に手をかけた。
中に入り、涼子がバ−テンダーに目で合図すると、手ですっと奥のカウンターを示される。
狭くもなく広くもない、適度に照明が落とされた雰囲気のある店内には、低くJAZZが流れている。
止まり木に腰掛ける涼子に軽く手を貸すと、泉田もその隣に腰を下ろした。
「食べ物を少しちょうだい。それと、ん〜スコッチでいい?泉田クン。」
「結構です。」
帆船の絵がついたウィスキーのボトルから、琥珀色の雫がグラスに注がれる。
乾杯を終えると、2人の話題は、店の名に由来した推理小説へと移っていった。
ジューシーで小さな鳥の唐揚やキャビアのオープンサンド、新鮮なベジタブルスティック、
どれも美味しく、ほどよくお腹を満たし、ボトルは順調に中身を減らす。
お気に入りの推理小説の話題はたあいなく、時に物騒に、楽しい時間を醸し出してくれる。
泉田は、時々肩にもたれかかる涼子の重みを心地よく思いながら、ゆったりと飲んでいた。
しかし。
さっきから気になることがある。
まただ。
近くの席で飲んでいた二人連れが、どことなくそわそわと帰っていく。
これで店内の客は、涼子と泉田だけになった。
泉田は店に入って初めて時計を見た。まだ10時を少し過ぎたところ。
女王さまが、また気まぐれに何か魔法を使ったか?
今までも、涼子は何度か店を貸切にしてしまったことがある。
席を外していた涼子は、向こうでバーテンダーと何か話している。
泉田は戻ってきた涼子にたずねた。
「人が減りましたが?」
「そうね。みんな気をきかせてくれたのかもね。」
涼子は隣に腰掛けると、泉田の頬をつついた。
「2人きりはいや?」
「結構ですよ。」
泉田は年上の余裕ぶって見せた。
涼子はにやりと謎めいた微笑みを浮かべた。
そして。
「うわあ、きれい!」
真夜中すぎ、扉を出た泉田は息をのんだ。
ぶんっと音がしそうな勢いで振り返ると、そこには両手を広げ、空を見上げて歓声を上げている涼子。
その満面の笑みにきりりと奥歯を噛み締める。
彼女は知っていたに違いない。
「・・・謀りましたね。」
外は一面雪で真っ白。
空からはまだ、柔らかな白い結晶が少し早い速度で無限に落ちてくる。
既にかなり積もっているところを見ると、降り出しは遅くとも1時間以上前だろう。
そりゃ、みんな急いで帰るはずだ。
涼子が跳ねるように、雪に覆われた階段を上っていく。ヒールが雪に埋もれ、きゅっきゅっと音を立てる。
泉田はあわてて後を追った。
地上に出ても、車は超徐行でしかもまばら。
街は完全にその景色を変えていた。
人通りもいつもの週末とは全く違う。
帰るのをあきらめカラオケボックスの前でたむろっていた学生たちが、
楽しげに雪を踏みしめながら通り過ぎる涼子に見とれて、動きを止める。
「どうするんですか。タクシーも走っていませんよ。」
不機嫌というか、少し投げやりな声で泉田はたずねた。
涼子がくるりと振り返る。
「まったく、どうして無心にきれいな眺めを楽しめないかなあ。」
「すみませんね、風流を理解できない部下で。」
「本当に。」
涼子は泉田に腕を絡めて、また空を見上げた。
落ちてくる雪は、少し小降りになってきた。
しかし涼子のコートの肩はもう濡れて色が変わっている。
ヒールの足だって感覚がないほど冷えているはず。
「警視、雪がお気に召したのはよくわかりました。でも、このまま外にいると風邪をひきます。
せめて傘をさがしてきますから、どこか店に入りましょう?」
涼子はぎゅっと泉田の腕にしがみついた。
「いやっ!」
泉田は大きくため息をついた。
さすがにまばらとは言え人がいる中を、抱いて歩くわけにもおんぶをするわけにもいかない。
「寒くないから、大丈夫。もう少し、じゃあ公園のいつもタクシーが停まっているところまで、ね。」
涼子が泉田を見上げる。
涼子の髪の雪を払いながら、泉田は仕方ないと頷いた。
「わかりました。行きましょう。」
途中に通った駅の周囲は、すごい人だった。
電車は完全に止まっている様子で、内容は聞き取れないがアナウンスが繰り返し流れている。
タクシー乗り場には、とても今晩中にははけないと思われるほどの、長い行列が出来ている。
それを横目に2人は、いつも夜遅く電車がなくなった時にタクシーを拾える穴場である、
勤務先近くの公園まで歩き出した。
見慣れたビルも道も姿を変え、方向感や距離感がうまくつかめない。
その不思議な不安定さ。
「全く違って見えるね。」
「本当ですね。」
誰もいないオフィス街。さっき飲んだスコッチで、体がまだ温かいのが救いだ。
涼子はまた、ふわふわと舞い降りてくる雪に手を伸ばしている。
美しく紅潮した頬は本当に楽しそうで、それを見ているうちに、泉田にもようやくこの非日常を楽しむ余裕が出来た。
いつも事件で駆け回る街。
時に非情で単に雑踏が流れるだけに思える道は、白く輝いてまるですべての不浄を凍らせるようだ。
謀られたことはともかく、泉田もようやく少しだけ涼子に感謝する気になった。

「・・・やっぱりだめか。」
公園についたが、いつもタクシーが並んでいる場所には、一台も車がいない。
それどころか、時間がたつにつれて大通りを走る車もどんどん減ってきている。
「ねえ、泉田クン、あそこ。」
涼子が指差す先、公園の中の一角に、人が少し集まって、なにやら灯りがついている。
「行ってみようよ。」
涼子に引かれるままに歩くと、そこにはラーメンの屋台が出ていた。
いつもはもっと歩道近くで開いている店だが、雪を避けて木のある公園の中に入ったのだろう。
周囲では10人ほどのサラリーマンやカップルが、屋台であるいは立ったまま、ラーメンをすすっていて、
屋台の中では、泉田には馴染みの親父が忙しそうに働いている。
「あれ、兄さん、今日はえらくきれいな彼女連れだね。」
親父が屋台の中から目を丸くする。涼子は愛想よく微笑んで手を振った。
「親父さんこそ、こんな雪の中がんばるね。帰れないんじゃないかい?」
心配そうな泉田の問いに、親父は豪快に笑って答えた。
「ああ、もう帰ることなんてあきらめて、今日は一晩、玉が切れるまでいっそここで営業しちまえってね。
駅前でタクシーを待って冷えたお客さんが、話を聞いて結構流れてくるんだよ。
あったまってもらいたいからねえ。かかぁも呼んで、夫婦で夜通し稼いでるよ。」
「いらっしゃい。」
おかみさんらしい人が、後ろから声をかけて笑ってくれた。
「雪も止んだからね、あっちのベンチも拭いといた。座れるよ。あったまっておいき。」
どうしようかと泉田が涼子を見ると、涼子はうんうんと頷いた。
「じゃあラーメン2つね。」
「へいっ。」

渡された湯気の立つ器を持って、二人でベンチに座る。
一口食べて、涼子は思わず歓声を上げた。
「ん〜おいしいっ。あったかい。」
親父の言うとおり、食べている間にも、少しずつ駅の方から客が流れてくる。
近くのビルで残業を終えたなじみ客もひっきりなしに来る。
夫婦ともに休むまもなく、しかし笑顔を絶やさずその客たちを迎えている姿を見て、
泉田はぽつりとつぶやいた。
「いいなあ、こんな雪の中、一生懸命働いて人を幸せにして。なんかかっこいいですよね。」
「そうね、半分はラーメンに、半分はあの夫婦にあっためてもらってるって思うわね。最高のサービスよ。」
泉田は食べ終わった器を隣に置くと、屋台を眺めながら言った。
「こんな時、警官でよかったって思うんですよ。
あの人たちの安全を守る為に働いていると思うと、少し自分の仕事に誇りが持てます。
それにSPもいいけれど、やっぱり事件に関っている方がいい。解決出来たって実感も大きいですからね。」
涼子は、ラーメンの汁をすすりながら、そっと泉田の顔を横目でのぞき見た。
誇らしげに微笑んだ横顔には、重責もつらさも全て飲み込んだ凛々しさが溢れている。
「・・・一生懸命働いて、人を幸せにして、か。なんか、キミこそかっこいいじゃん。」
「え?」
小さなつぶやき声だったために、うまく聞き取れなかった泉田が聞き返す。
涼子はその問いには答えず、ごちそうさまと笑って器を置いた。
「さて、どうしますか?どこかなじみのホテルにでも泊まられますか?」
「ん〜JACESの車を呼んでもいいんだけどね。歩きたいな。」
「そのヒールで?5Kmはあるんじゃないですか。呼べるなら無理をしない方がいいのでは。」
「これ以上は降りそうにないわ。道が凍るとやっかいだけど、まだ大丈夫よ。」
公園の前の大通りはすっかり行き交う車も絶えて、路面が灯に照らされ淡い青をまとった銀色に輝いている。
「送ってくれるでしょ?足が冷たくてたまらなくなったらおんぶして。」
「はいはい。」
涼子は、苦笑いで答える穏やかな泉田の瞳をじっと見つめた。
泉田がどうしたのかと首をかしげる。
――謀ってごめんね。
でも雪の夜には、絶対そばにいてほしいと思っていたの。――
涼子は声には出さない思いを胸にかすかに微笑むと、温かな泉田の腕に寄り添い歩き始めた。
(END)
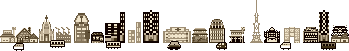
*天気予報はしっかり見よう、泉田クン(笑)。
長くなってごめんなさい。本当はバーから出てきたところと一番最後をくっつけて終わりでもよかったんですが、
どうしても泉田クンのかっこいいシーンをもう一つ入れたくてこんなことに。
設定詳細、中に出てきた小説の内容や、「帆船の絵柄のウィスキーって?」と興味を持ってくださった方は、
よろしければどうぞ「2月23日更新記録」の日記へお越しください。ありがとうございました。